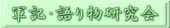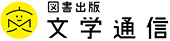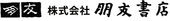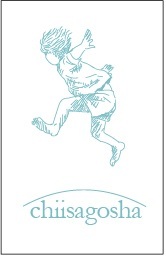目次
第一章 それは比叡山から始まった――明治四十四年夏期巡回講演会への道程――
一、夏期大学の先駆「叡山大講演会」
比叡山大講演会とは何か/多彩な講師陣/仏教、老子と社会貢献/軍人の講演もあった/日露戦争二年後の軍事情報
二、講演の場は聖なる地
なぜ比叡山が選ばれたのか/高野山と比叡山の違い/山上に至る道/宿坊と聖域/受講生の職業はさまざま/親睦を深めた会員たち/関東を経て再び関西で実施/自粛ムードを払拭する開催
第二章 関西各地を巡回した講演会
一、漱石、天囚、湖南が登壇した巡回講演会
三班に分かれた講師陣/世界情勢を受けた時事的講演/夏目漱石の登壇/演題と会場/航空機の時代へ/悲劇を乗り越えて/歴史と文化に関わる講演
二、大阪中之島での大講演会
中之島公会堂を会場に/内国勧業博覧会と大阪/明治三十五年に開場した公会堂/四千七八百人の前で/大観衆を容れる劇場の文化/近代大阪の講演会場/地声かマイクか/国会と宝塚歌劇のマイク導入
第三章 西村天囚の講演「大阪の威厳」
一、講演録の形成
速記によって記録された講演/近代速記術の歴史と実用化/言文一致運動と速記/筆記具と速記の変化/講演の草稿はあったのか
二、「大阪の威厳」全文注釈
大阪の威厳/文化が生み出す威厳/富の力と文化/大阪の富と学問/江戸時代大阪の学問の隆盛/片山北海と混沌社/麻田剛立と富永仲基/町人学者と懐徳堂/山片蟠桃と大阪/大阪の蘭学/大阪文化の伝播/文化と品性と信用/維新後の大阪/博物館、図書館、大学の必要性/旦那学こそ重要/紳士学のための大学創設/学会と出版界/写本から版本へ/金を有益に使う/紳士団の事業
三、「大阪の威厳」の特色と意義
時系列で組み立てる/「世界一周会」を反映した講演/欧米で見た大学/グーテンベルクと日本の写本/文化を支えるインフラ/学術文化のためにお金を活かす/天囚の活動を後押しした世界旅行体験/「威厳」から見た都市論/都市の抱える病理/近代教育史と懐徳堂/懐徳堂の教育理念と学費/発見された講演の設計図
第四章 道徳・学問・宗教と日本
一、威厳を支える精神
天囚の考える「精神思想」とは/「精神」と「道徳」の原義/もう一つの講演「国民道徳の大本」/「国体」とは何か/我が国固有の道徳と儒教との関係/儒教の伝来/明治維新と「新学新説」/教育勅語と儒学/儒学復興の兆し
二、道徳と教育勅語と儒学
速記で残る下賜三十年記念講演/天囚の草稿『教育勅語私見』/重野安繹『教育勅諭衍義』との関係/科学と精神、時代と道徳/古典・歴史と教育勅語/講演「朱子学派の史学」の意義/懐徳堂の学風/懐徳堂で孔子は祭られたのか
三、西村天囚と「孝」の思想
横綱西ノ海の顕彰碑/天囚の「力士西海報恩碑」〔相撲の歴史/西ノ海の経歴と報恩の思い/孝は得難し〕/『碩園先生遺集』との相違/相撲の歴史とその特色/西村家に残る西ノ海土俵入りの写真/日本の相撲は神聖な武道/西ノ海と天囚の「孝」
四、儒学とキリスト教
新たな時代にふさわしい日本的儒学を/新旧文明の調和を目指す/天囚は世界旅行でキリスト教をどう見たか/大隈重信とタゴールの説く「調和」/懐徳堂再建運動におけるキリスト教の問題/「懐徳堂にキリストとマリアの像を」/神道、仏教、儒教と懐徳堂
五、完全収録四講演〔「朱子学派の史学」/「国民道徳の大本」/「懐徳堂の由来と将来」/「教育勅語衍義」〕
第五章 講演と近代人文学
一、日本近代の学術と講演
西村天囚の話しぶりは/郷里種子島の習わし/そのまま大阪学問史に/漢語の教養とコミュニケーション能力/夏目漱石の語る「演説」と「講演」の違い
二、演説・講演の歴史と意義
「講演」とは何か/福沢諭吉と明治時代の「講演」/弁論ブームの到来/世界を動かす声の力/西洋流スピーチの導入/身振り手振りを交えて/未分化だった演説と講演/摘発された政談演説/演説会から学術講演会へ
三、明治時代著名人の話しぶり
速記者が見た名士の演説ぶり/「速記者泣かせ五人男」/一分間に五百五十音/聴いても書いても良い/早口、長い、一本調子/雄弁家として評価されるには
四、漢学者の話しぶり
天囚の口調はゆったりしていたか/重野安繹の話しぶり/昌平坂学問所の話しぶり/江戸の漢学者から天囚へ継承された話しぶり/「抑揚頓挫」のある講演/中井竹山の修辞法を読んでいた西村天囚/一人称「我輩」と二人称「諸君」/講書始とはどう違うのか/整然とした構成と言語/講演を支える情熱と気魄
五、漢学と近代人文学
天囚の講演と日本近代の学問/まずは素読から/漢学をハブとする学問の再編/実現した天囚の夢
関係年表/参考文献/画像出典
おわりに
索 引
内容説明
明治44年(1911)夏、西村天囚、内藤湖南、夏目漱石など著名な文人たちが関西各地を巡回する連続講演会を実施した。
その最終日に大阪中之島公会堂で開催された大講演会で、西村天囚は 「大阪の威厳」と題する講演を行った。明治・大正時代を代表する漢学者・ジャーナリストであった天囚が近代大阪に期待した「威厳」とは何だったのか。その真相について、天囚の郷里種子島で発見された自筆草稿と講演録を参考にして考察する。
第一章では、その先駆的業績と考えられる明治40年の「比叡山講演会」に注目し、第二章では、この夏期巡回講演会の全体像を明らかにする。
そして第三章が天囚の「大阪の威厳」講演である。ここでは講演全体を便宜上全20節に分けて詳しく解説する。また、その前提として、当時の講演が「速記」によって記録されていることにも注目し、日本近代の速記法の歴史と意義についても考察する。
その後、第四章では、この「大阪の威厳」講演の基盤ともなっている学問と教育、精神と宗教の問題について、中国古代にさかのぼって考察し、最後の第五章では、改めて天囚の講演の特徴を同時代人の証言から分析し、郷里種子島で行われていた朗読の習わしについても注目する。また「演説」「講演」の歴史をたどり、福沢諭吉、伊藤博文、嘉納治五郎、渋沢栄一など明治時代の著名人の話しぶり、および江戸時代以来の漢学者の話しぶりとも比較しながら、日本近代の学術文化にとって、天囚の講演がどのような意味を持っていたのかをまとめてみたい。