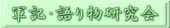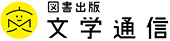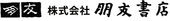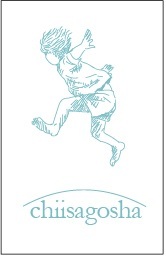目次
第一節 緒論
第二節 秦漢帝国史論の展開
第三節 本研究の位置付け――爵制的秩序と異なるアプローチ――
第四節 本研究の視角――符の政治的な価値――
〔符と皇帝権力/符の賜与――「剖符」の語義――〕
第一章 符による権力構造論の研究射程
第一節 符研究の問題点
第二節 符をめぐる諸研究〔符の種類/出入符の分析/先行研究における符の理解〕
第三節 戦国秦漢における符の継承〔符継承の系譜/符の出現時期〕
第四節 秦漢時代における符の連続性〔律令規定の継承/地域観念の変遷〕
第二章 帝国形成前史の符――「置質」「剖符」に支えられた戦国時代の国際秩序――
第一節 戦国時代における剖符の意義
〔戦国時代における「国符」の使用/漢によって継承された秦符/国符を用いた関所通過〕
第二節 春秋戦国に見える「借道」〔剖符と置質との牽制/春秋・戦国における借道の事例〕
第三節 質子による符の使用
第三章 出土文物に見る秦漢虎符の形成と発展
第一節 出土文物による節への理解――林・大庭説の再検証――
第二節 『周礼』に見える節の法則性
第三節 戦国秦漢の虎符〔伝世史料に見える虎符の使用/銘文に見る虎符の時代性(左右同文型/左
右合体型)〕
第四章 前漢時代の竹使符――「徴」の分析を通じて――
第一節 竹使符と顎君啓節
第二節 秦漢時代における「徴」の事例
第三節 地方から中央への徴召と出入〔地方官吏の徴招/皇帝位継承者の招聘〕
第四節 竹使符と「漢家天下」
第五章 漢初における符の下賜
第一節 高祖と功臣との剖符
第二節 漢王国の支配体制――諸侯王との剖符――
第三節 符を剖かち世々絶ゆる勿し――列侯との剖符――
第四節 徹侯から列侯へ
第六章 扜関によって連結された秦漢帝国の南方交通――漢越外交に介在する符の役割――
第一節 「津関令」に見える扜関の位置付け
第二節 扜関の北上交通
第三節 扜関の南下交通〔長沙地域との接続/南越王国との接続〕
第四節 符によって結ばれる漢越の外交
第五節 扜関の管轄形態――諸関所と合わせて――
終 章 総括と今後の展望
第一節 総括
第二節 今後の展望
〔中国古代帝国が持つ二面性――在地社会への考察――/交通規制を解除する諸媒体/日
本への伝播〕
附 章 始皇帝の二六年巡行をめぐって
第一節 『嶽麓秦簡』に見える始皇帝二六年巡行
〔制詔年代の特定/本条の構成員について/始皇帝一行の目的地について/始皇帝一行の
経路について/始皇帝の二六年「巡行」〕
第二節 湘山での行いの矛盾――二八年巡行との比較――
第三節 周縁地域への巡察――二七年巡行との比較――
第四節 二六年巡行と南方攻略
附録一 伝世史料に見える符の記載
附録二 符の熟語
引用・参考文献一覧
内容説明
【「序章」より】(抜粋)
これまでの国家構造論においては、歴史地理学的な観点を取り入れながらも、特定の地域の分析に偏り、地域を越えて移動する人々への考察が欠如しており、広域な領土支配の問題に取り組むのに不足を感じざるを得なかった。したがって、交通の観点を導入しつつ、いま一度古代中国の権力構造を再検討し、帝国形成史における人々の移動の実態と、皇帝支配との関連性を追究することが、当面の課題であると考えられる。本書は、従来の国家構造論の限界を克服し、人的往来の観点から古代中国の権力構造を新たに検討することを目指している。すなわち、特定地域への偏りを排して、広域な領土支配の問題に取り組むため、人々の移動の実態と皇帝支配との関連性を、交通の視点から解明しようとするものである。